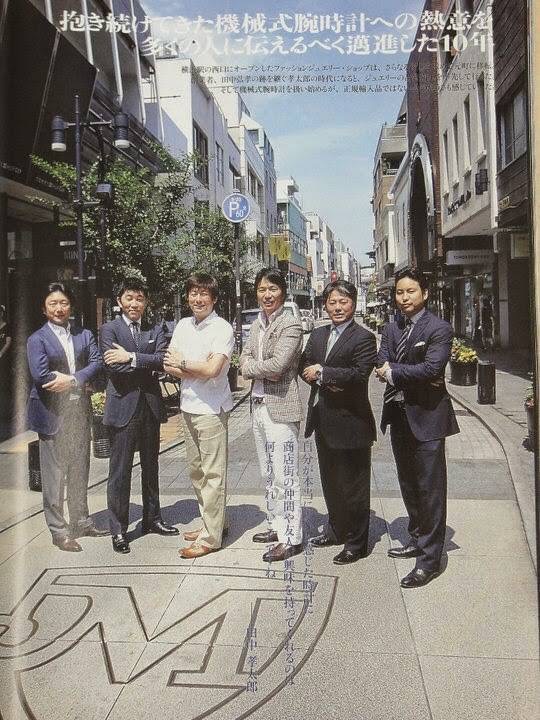少し話しは変わるが、私は洋服や靴や鞄などが大好きである。実はこれは今に始まったことではない。高校時代に、原宿や渋谷や元町あたりの古着屋を回ってインディゴのジーンズやジージャンを探し回ったりしていた頃からのことである。今まで、洋服や靴やバッグや小物類にどれだけの金額を使ったことか・・(笑)。そういったものと同じように、機械式時計への興味が湧いてきたのも極自然のことだったように思う。私が時計を見る目というのは、今でもファッションの一環として見ている面が強いのは、こういったことが影響しているのだと思う。とはいっても、表面的な流行のファッションという意味ではない。クロケット&ジョーンズやエドワードグリーンの靴の様にインコテックスのパンツ、ボレッリのシャツの様に、グローブトロッターのトローリーケースやエッティンガーの鞄の様に・・・。伝統があり、流行に左右されず、頑固なまでに守り通す何かがあり、そして文句無く不変的な美しいデザインであるという意味でのファッションである。だから、常に私が時計を選ぶときには、そういった目線で選んでいるのである。この時計は時代に媚びていないか?長く使うための工夫がされているのか?不変的で美しいのか?自分が欲しいか?友達に薦められるか?そんなことを大事にしてきたつもりだ。私が父の会社を手伝い出した当時は機械式時計というものが世間ではまったく認識されていない時代であった。それどころか時計についての雑誌も殆んど出ていなかったような時代でもあったから、アンティーク時計屋のオヤジが私の機械式時計の師匠でもあった。私が初めて自分で購入した機械式時計は、1960年代の14金のアメリカへの輸出向けのルクルトのものだった。
私が生まれ育った横浜の本牧や元町界隈には、今思うと独特の文化があったのだろうと思う。私が小学校の低学年まで住んでいた本牧には、当時まだ広大な米軍の住宅地があり、そこを地元では「外国人ハウス」などと呼んでいたりした。通りを挟んだ向こう側が、まさに柳ジョージの歌の「フェンスの向こうのアメリカ」だったのである。その敷地内にこっそりと入ってはアメリカ坂でスケボーをしたことなどを懐かしく思い出す。当然すぐにポリスに摘まみ出されたことは言うまでもないが・・・(笑)。当時の洋楽は全てこの「フェンスの向こうのアメリカ」から発信されて本牧のライブハウスで演奏されていたと聞いている。そして、そういった最新の音楽を聴きに多くの人が東京からこの地にやってきたのだそうだ。
そんな地域にいたからかもしれないが、私が得る情報は媒体を通さない生のものが多かったように思う。近所の走り屋から車の話しを聞き、ジャズバーやライブハウスで音楽に触れ、洋服屋のオヤジからファッションを教えてもらった。社会人になってからも、元町にある信濃屋の白井さんからスーツや靴の何たるかを教えてもらったりしたのも極自然の出来事だったのだ(後に雑誌を見て凄い人だと知ることになるのだが・・)。もちろん機械式時計にしてもそうだったということは前述した通りだ。そうやって、機械式時計に触れているうちに、その魅力に取り付かれ自分でも扱ってみたいという思いが強くなっていったのである。
今みたいに雑誌やネットでの情報が氾濫している時代でもなかったので、大して考えもせずにショップの片隅に機械式時計を置いてみることにしたのだ。
しかし現実は厳しい。いざ自分の好きな時計を置こうと思っても、実績のまるでないショップに商品を出してくれる正規輸入元など皆無に等しいのである。当然、ブライトリングやIWCなんてまったく相手にしてくれないのである。しかし、そんな中で相手にしてくれたブランドがひとつだけあった。ゼニスである。しかし、何度も言うが機械式時計は見向きもされていなかった時代である。ピラーホイール(高級時計の機械パーツ)がどうとか、36000振動(振動数が高いほど時計は正確と言われていて、3万6,000振動は最高クラス)がどうとか、スライディングギアがどうとか誰も興味がないのである。ゼニスの商品の前で足を止めてくれる人がひと月に一人か二人いればいい方だというくらいの寂しい時代であった。何ともこの先不安にさせられる機械式時計業界への一歩踏み出したのである。今から30年以上前のバブルが崩壊した頃のことだ。
世の中がこれからどうなっていくのかという不安と、機械式時計を面白いと思ってくれる人なんかいるのだろうかという不安。二つの大きな不安を抱えて横浜時計物語の幕は上がっていくのである。